この記事は
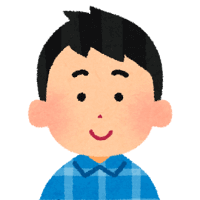
「先生、『疑似分裂文』っていったい何でしょうか?通常の強調構文(分裂文)は知っているのですが、何か違いがあるんですか?」
と疑問に思っている英語学習者に向けて記事を書いています。
● みなさんこんにちは、まこちょです。
唐突ですが、みなさんは「疑似分裂文」というネーミングを聞いたことがあるでしょうか?
分裂文というのは「強調構文」の別の呼び名と思ってくださって結構なのですが、It is~that(who / which)…などの強調構文については、当ブログで記事にしたことがあります。
参考までに


強調構文もいろいろな形があって、正直面食らった方も多いのではないでしょう。参考までにこれまでの記事について過去記事を載せておきますね。
さて、今回ご紹介する内容なのですが、もしかしたら「え?これも強調構文(分裂文)なの?」と驚いてしまうかもしれません。
It is ~ that…などの強調構文は学校や塾などでもよく取り上げられることから、案外「形」的にはお馴染みなことが多いのですが、今回ご紹介するこの形は「強調構文(分裂文)」の枠組みから外されてしまうことが多いですので注意が必要です。
そう、それは「疑似分裂文」と言われるもの。
「疑似分裂文?何それ?」と思った方、多いんじゃないでしょうか。以下のような英文を指すのですが見たことがあるかもしれません。
例
All I have to do is (to) wash the window.
この英文は一種の「強調構文」なのですが、いったいこれのどこが強調構文なのでしょうか。そこで今回はこの疑似分裂文について徹底解説!
通常の分裂文(強調構文)と一体何が違うのかをみなさんと確認していきましょう。ぜひマスターしていただいて、今後の英文解釈にお役立てくださいね。
以下の記事をお読みいただくと、次の点であなたの英語力は向上します。
▶「疑似分裂文」と通常の分裂文はいったい何が違うのかが分かる
疑似分裂文とはいったい何か??

先ほどの例文をもう一度確認してみますね。
例
All I have to do is (to) wash the window.
この英文は大学入試などでもおなじみの構文ですが、この英文は
All(S) ← [(that) I have to do] is(V) [(to) wash the window](C).
とSVCの第2文型の構造を持っていることを理解しましょう。Allが主語(S)なんです。したがって訳は
「私がしなければならないことといったら、皿を洗うことだけだった」
と解釈します。このとき重要なポイントは、It is ~ that…の強調構文は「~」の部分が強調したい場所なのですが、上記の構文は【be動詞の後ろの部分(C)が強調したい場所】だということです。
① It is ~that…
→ 「~」の部分が強調する箇所
②All S have to do is (to) do…
→ 「be動詞の後ろ」の部分が強調する箇所
このような強調構文(分裂文)の一種を「疑似分裂文」というのですが、be動詞の後ろの部分を必ず強調するという点で非常に分かりやすいんですね。
疑似分裂文の種類
この疑似分裂文ですが、他にも種類があります。特徴は共通していますのでしっかり覚えておきましょう。
①主語が All +関係代名詞節 / The only thing +関係代名詞節 / What節
②be動詞以下の補語(C)の部分が強調されている
例
The only thing he knew was that she needed help.
「彼が知っていた唯一のことは、彼女が助けを必要としていたということだった」
強調部分は that she needed help
例
What we want to do after school is (to) play basketball in the gym.
↓
[What we want to do after school] (S) is (V) [(to) play basketball in the gym] (C).
強調部分はto play basketball in the gym
「私たちが放課後したいこととは、体育館でバスケをすることだ」
なかなかパンチの利いた形をしていますが、実は慣れるとIt is ~ that…の強調構文より見分けやすいです。
例えばIt is ~ that…は同じ形に「仮主語構文」もありますし、Itが「代名詞」のthat以下が関係代名詞節のときもあります。
それに対してこの疑似分裂文はある程度形が決まっている上に、強調する箇所が【必ず】be動詞以下、という点ではっきりしているので、実は「楽」なんですね。
疑似分裂文についてちょっと深い話
最後にちょっと疑似分裂文について「深い」話をしましょう。
この疑似分裂文は、特徴としてbe動詞以下を強調するとありますが、be動詞以下の内容は読者にとって必ず「新情報」であるという特徴があります。
つまり読者にとって初めて知った情報ということになりますね。
なぜこのようなことを唐突に言うのかというと、これまで学習してきたIt is ~ thatの構文ですが、「~」の中に入るものは必ずしも「新情報」とは限らないからなんです。
例えば以下の長文をちょっと読んでみてください。
More often than not, cities are seen as problematic – with congestion, pollution, poor housing, collapsing infrastructure, crime and poverty. But it is cities that drive economics.
[単語・表現]
more often than not 「しばしば」
problematic「問題の根源」
congestion「混雑」
poor housing「住宅事情の悪さ」
collapsing infrastructure「インフラの崩壊」
drive「先導する」
和訳「しばしば、都会は、混雑や、公害や、住宅事情の悪さや、インフラの崩壊や、犯罪や貧困などが、問題の根源として見られる。しかし都会が経済をけん引しているのだ」
この英文はBut以下が強調構文なのですが、It isとthatの間に入っているcitiesは「新情報ではありません。
その前の英文で散々citiesについての内容が書かれているのですがIt is~thatの強調構文はこのような使い方もされるということです。
ところが今回の疑似分裂文はbe動詞以下が【必ず】新情報になるという点で、実はIt is ~that…の強調構文よりも狙いがはっきりしているのは押さえておくべきでしょう!
なお「新情報」「旧情報」に関するノウハウは以下の記事を参照してくださいませ。
↓↓↓↓↓
「「情報構造」って一体何なのか徹底的に考えてみた!(基礎編)」
「there ~、because S+V~、CVS「倒置」など、「情報構造」を意識する文はこれだ!!」
疑似分裂文についてのまとめ

さて、今回は「疑似分裂文」について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
疑似分裂文についてまとめると以下になります。ぜひリーディングの際には注意して下されば幸いです。
【疑似分裂文まとめ】
①主語が独特の形をしている
②文型はSVCの第2文型
③強調する箇所はbe動詞の後ろ(Cの部分)
④Cは必ず「新情報」になる
ぜひ今後の英語学習にお役立てください!また会いましょう。




コメント
素晴らしい解説でした。